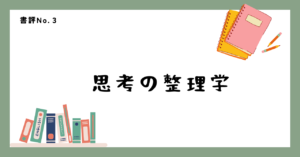20年程度家の本棚で眠っていた外山滋比古先生の「思考の整理学」を読んだので感じたこと、気づいたことなど書き連ねます。
私があえて強調するまでもないですが、時代を超えた名著。
筑摩書房さんのWEBサイトで、本書は学術エッセイと紹介されていますが、
「もっと若い時に読んでいれば…」と思わずにはいられませんでした。
元さわや書店 松本大介さん
まさに、読み終わった後の感覚はこんな感じでした。こちらを帯に採用されている筑摩書房さんのセンスもさすが。
 George(父)
George(父)40年前に書かれた本(自分が生まれたころ)とは思えない先進性、普遍性。本書に影響を受けて、個別テーマを深掘りしていったビジネス書もたくさんありそうです



本よりマンガ派な僕も、お父さんに勧められて読んだよ。昔の本だけど読みやすかった
- まだ本書を読んだことがない全ての人
- 仕事がなんだかうまくいかない、考えがまとまらないという悩みを抱えている方
- ビジネス書や自己啓発本が好きな方
この記事を書いているGeorge(父)は、都内在住サラリーマン(妻1人子供3人)。不毛な通勤時間をほぼ全て読書に費やし、年間100冊程度の本を読んでいます。自らの備忘も兼ねブログに書き留めることをはじめました。



本を読んだきりになると、もったいなーと思って…
\ それでは、いってみましょう /
基本、全編通して面白いのですが、特に共感・参考になったこと3点ご紹介します。
グライダー人間になってはいけない
外山さんは、受動的に知識を得るのみで自ら考え行動することができない人を「グライダー人間」、推進力を有し、自力で飛翔できる人を「飛行機人間」と定義しています。
ある程度のグライダー能力がないと飛ぶことすらできないので、2つのバランスが大事なのいうまでもないですが、学校教育はグライダー能力の獲得に重きが置かれすぎているとの課題を提起しています。
ITやAIの登場を受け、今でこそ活発に議論されてる論点ですが、40年前(バブルの前ですよ!?)にすでにこの問題を提起されている外山先生の隻眼にただただ感服。
「コンピューター」という飛び抜けて優秀なグライダー能力の持ち主があらわれたのだから、子供が疑問を抱き、好奇心を働かせる前に教えてしまいがちな、現在の学校教育は変わらなければならないと主張しています。



ChatGPTのような生成AIがどんどん発展してくると、飛行機人間にならないとしんどそうです……



計算、漢字、英単語…覚えること多すぎて疲れるけど……
最近は、クラスで議論したり考えてみようという授業も増えてきたよ



自分もどちらかといえばグライダー人間。
本を読んで知識溜め込むだけではなく、本から得た知識や気づきを自分なりに咀嚼して、仕事や生活に取り入れて行かないとなぁ…というのもブログを始めた理由の1つです
朝飯前
朝飯前ということば。
辞書には「朝の食事をする前」、用法として「そんなことは朝飯前だ(=簡単だ)」とあります。
朝飯前の本当の意味は「決して簡単ではないことが、なぜか朝だとささっとできてしまう」ということではないか。
というのが外山さんの見解。
皆さんも夜にどんなに考えても解決しなかった問題が、朝になったらなぜか解決したという経験があるのではないでしょうか?
昔から、「早起きは三文の徳」と言われますし、脳科学者の茂木健一郎氏も起きてからの2時間がゴールデンタイムと言っています。
クリエイティブな職業の方などは、アイデアに悩んだときは意識的に仮眠を取ったりされてますよね。
「睡眠こそ最強の解決策である」の著者、マシューウォーカーさんが睡眠の効能を研究することになったきっかけは、ある有名なピアニストが何度練習してもスムーズに弾けない箇所も、朝起きて弾くとなぜか弾けるようになっている、と聞いたことだったとか。



ブログの文章も、あらためて朝に読み返してみると、しっくりくる表現や構成が浮かんできます。
今でこそ、脳科学や睡眠に関する研究が進んできて、睡眠と朝活が推奨される時代になりましたが、これも外山先生は40年前に書かれているんです。
睡眠時間を削ってを働くことが当たり前と考えられていた時代にです。びっくりです。


しかも、これだけで終わらないところが外山さんの素敵なところです。
早起きすることが苦手な人向けに、朝飯を抜いて昼食とセットのブランチにして、しっかりとした昼寝をすることを勧めています。
これにより、朝飯前が2回に増えるからといって自ら実践しているとのことですw



しっかりお昼寝するくらい、朝飯前🎵
忘れることは自然なこと
最近、物忘れがひどい、暗記ができなくなってきた、等々悩まれていませんか?
そんな方は、ぜひ本書を手に取ってみてください。前向きになれます。
子供の頃から忘れてはだめ、忘れてはだめと言われて育つから、忘れることはとてもいけないことという偏見がありますが、本当は、頭の整理のためには忘れるがことがとても大事。
人間の頭を倉庫として捉えると良くない印象を受けてしまう忘却ですが、そこはコンピューターに任せれば良い領域。
脳を新しいものを生み出す工場として捉え、能率をよくしようと思えばどんどん忘れる必要があるよ、忘れたと言って落ち込む必要はないよと。
もともと、人間は自然に忘れるようにできていて、それが先ほども出てきた睡眠の効用の1つ。
朝に頭がすっきしているのは睡眠のおかげなんです。
どんどん摂取したらどんどん排泄するというのは自然の摂理。
忘れたいことほど、逆に忘れられないものですが、たとえ忘れることができなかったとしても、
頭を効果的に整理する方法として、運動(散歩)や休憩、お茶を飲む、など、全く別のことに取り組んで気分転換することが重要であると提案されています。



暗記系のテストの点数が悪くても反省する必要なし



次から次へ興味関心が変わって、飽きっぽい自分の性格も自然の摂理なのだ
人間の集中力はそう長い時間は持続しない。25分やって5分休憩のサイクルを繰り返すポモドーロ・テクニックが流行していることを考えると、外山さんの先見性はやはりすごいですよね。
\ 最後に一言/
思考の整理学、いかがでしたでしょうか。
内容も素晴らしいのですが、外山滋比古さんは言語を研究されているからなのか、文章に着飾った感じがなくてとても読みやすいです。
昔の本ですが、そこは安心して読んでみてください。
外山先生は他にも面白い本をたくさん書かれていますので、機会見つけて本ブログへ感想などをアップしていきたいと思います。



最後まで読んでくれてありがとうございました〜






\1ヶ月の無料体験実施中🎵/
Amazonのオーディオブック Amazon Audibuleはこちらから
\ にほんブログ村参加中〜クリックしてね/