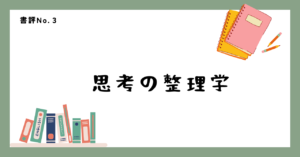養老孟司さんの「バカの壁」を読みましたので、感じたことなどを書き連ねたいと思います。
2003年出版。
私が社会人になったばかりの頃にとても話題になり、2020年時点で440万部以上を売り上げている大ベストセラー。
平成で一番売れた新書だとか。
つい最近、落合陽一さんと養老孟司さんのTheインテリ対談的なyoutubeを拝見したのですが、
昔と変わらない養老節に触れ、読んでみようとなったわけです。
 George(父)
George(父)出版当初から「バカの壁」という得体のしれないタイトルに惹かれつつも、流行り物に手を出すのはなんだかなーと思って積読に……
- 「バカの壁」というタイトルが気になる方
- 長年積読になっている、昔読んだけどイマイチわからなかった方
- 議論が噛み合わないなと日頃悩んでいる方
この記事を書いているGeorge(父)は、都内在住サラリーマン(妻1人子供3人)。不毛な通勤時間をほぼ全て読書に費やし、年間100冊程度の本を読んでいます。自らの備忘も兼ねブログに書き留めることをはじめてみます。
\ それでは、いってみましょう
「バカの壁」ってなに?
「バカの壁」。とても気になるタイトルです。およそ99%の方が、
タイトル買いされたものと勝手に想像していますが、私もその一人。
そして、第一章がまさに“「バカの壁」とは何か”というお題。気になっていた疑問がすぐに解ける!
と期待に胸を胸を膨らませて読み進めますが、私にはさっぱり理解できず。
自分の読解力のなさを棚にあげ、「養老先生は偏った意見の持ち主なのではないか」、
「自分とは意見が合わない」などと感じていました。
最後まで読めば理解できるのですが、これも自分の中で「バカの壁」がなせる技でした。



正直なところ、途中で本を閉じようと思ったことが……



この記事は最後まで読んでね
中盤以降もわかったようでわからない
2章のタイトルは「脳の中の係数」。
自分の知りたくないことに全く耳を貸さない人が世の中にはたくさんいて、これが悲惨な戦争や争いにつながっている。
この仕組みを脳の視点から理解するためには、脳のへ入出力をシンプルな一次方程式 ”y=ax”と表してみるとわかりやすい。
この式のうち、係数の “a” が人それぞれで違っていて、“a” がゼロであれば無反応となるし、
“a” が無限であれば極端な原理主義につながる。
係数“a”は、その人の育ちであったり環境であったり、何がどの程度関係しているのかはわからけれど、みんなが持っていて、この係数“a”が人の行動や感情に大きく影響しているという。



要するに、この係数”a”が0だったり、無限大だったりするのはあまりよろしいことではないという立場
以降の章は、「個性を伸ばせ」という欺瞞、「万物流転、情報不変」、「無意識・身体・共同体」、「バカの脳」、「教育の怪しさ」と続きます。
どの章も興味深い内容ではあるけれど、全体を通じて何を主張されようとしているのか、養老孟司さんの意図がいまいちピンとこないなぁ……というのが本音。
特に、子供の個性を伸ばすことをを是とする教育は間違っているという主張。
安定した社会を維持するには「共通性(ルール)」が必要であり、言語もそれを助けている。
にもかかわらず、個性を伸ばせとは何事か!と書いてある。
子育て中のわが身としては、これには納得できずに困りました。



なんだかモヤモヤする
バカの壁を超えるために
モヤモヤしながらの最終章。
タイトルは「一元論を超えて」。
ここまで読んでようやく、本書を通じて養老孟司さんが何を伝えたいのか、が理解できたように感じました。
ようやく辿り着いた最終章で、「バカの壁」の正体(=著者の主張)がはっきりしてきます。
「バカ」というのは、自らの凝り固まった考え(さっきの”a”のことです)が悪さをして、「思考停止に陥っていること」、「(安易に)わかったつもりになっていること」であり、
そうさせている要因、つまりは、「一元論(根拠のない思い込みや偏った信念)」的な考えやものの見方のことを「壁」と定義しているということ。
2章から7章は一元論に陥りやすいテーマを用いて、一元論に落ちいることの危うさを説明されていたのです。



意識と無意識、脳と身体、都市と田舎、経済の虚と実。本書の中で出てくるこれらの対比は“二元論”になっています
バカにとっては、(一元論の)壁の内側だけが世界であり、壁の向こう側が見えない(見ようとしない)。
日本も世界も一元論がはびこっていることに警鐘を鳴らしています。
いわゆる一新教を是とする宗教対立もこの一種であり、
「あの人たちとは話が合わないからほおっておこう」とはならなず、
「あいつらは悪魔だ」と言い合っていて、場合によっては戦争に発展。
このような一元論に憑かれた人が世界人口の約3分の2を占めるという事実。
安易に「わかった」、「話せばわかる」、「絶対の真実がある」などと思ってしまうのも一元論につながる危うい姿勢。
最後まで読んで、ようやく著者の主張が理解できました。
これを受けて自分なりに考えたこと。
最近、「フードロス撲滅」をスローガンに、市場で売れない規格外の農産物を安く消費者へ提供するマッチングサービスがありますがあり、とても肯定的に捉えられています。
特に農産物の価格については、結局のところ需給のバランスで決まっているので、全体で見れば農家の所得を増やすよりも減らす方向につながっている可能性が高い(安い規格外品に規格品の価格が引っ張られてしまう)。「持続可能な農業」という視点から見ると「フードロス撲滅」は完全な正義とも言えないのではないか。一元論にならないとはこんな感じ?
本書を読んで、どんな時も多面的な視点は持ち合わせておくことが重要であることに気づきました。
正直、わかったようでわからないというのが本音ですが、それをありのままに受け入れるという姿勢も大事なのだと思います。
ただ、このバカの壁を意識し過ぎると、主張すべき時に主張できなくなり、
バカの壁で囲まれた世界の生きる人の間違った主張に負けてしまう危険性もありそうだな。。。
などとも感じたのでした。
さすがのベストセラー。
読んでジらされる点(私だけ?!)も含め、奥深い一冊です。
ぜひ、読んでみてください。



一元論に警鐘を鳴らすという主旨もあってか、あまり断定したトーンで書かれていない点もモヤモヤを感じた理由だったのかな?



お父さんには、ゲーム=悪、勉強=善という「バカの壁」を取り払ってくれると嬉しいのだけど…
最後に一言 /
バカの壁は最終章から読むべし!




\1ヶ月の無料体験実施中🎵/
Amazonのオーディオブック Amazon Audibuleはこちらから
\ にほんブログ村参加中〜クリックしてね/