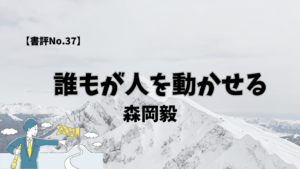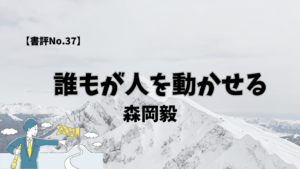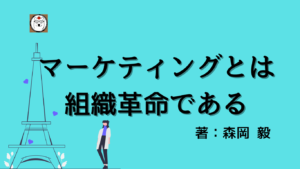USJ復活の立役者であり、日本を代表するマーケターである森岡毅さん。
現在は、USJを退職。株式会社刀(かたな)を立ち上げ、沖縄北部に話題のテーマパーク「JUNGRIA(ジャングリア)」を建設中。
そんな森岡さんが、「人」の力を最大限に活かす組織作りの本質と1人のサラリーマンが「組織」を動かすためのポイントを解説したのが、本書「マーケティングとは組織革命である」です。
 George(父)
George(父)今回は、読めば必ず胸熱になれるこちらの本をわかりやすく紹介します
この記事を書いているGeroge(父)は、都内在住のサラリーマン(管理職)。
通勤電車のほぼ全てを読書に費やし、ビジネス書を中心に年間100冊程度の本を読んでいます。(プロフィール)。
- ヒトの力を最大限に引き出す森岡流の組織作りに興味がある方
- 組織の中でやりたいことがあるけど、企画が通らなくて悩んでいる方
- 森岡毅さんのファン
\ それでは、いってみましょう
理想の組織(会社)とは?
あなたの理想の組織ってどんな組織ですか。



仕事がラクでお給料が高い会社



……
もちろんそのとおりなのですが、世の中にそのような会社はあっても少数であるという現実に立ち戻ります。
組織とは本来、社員一人一人の能力を引き上げる装置であるべきなのに、組織にいると力が引き出されるどころか、個人として削られていく…….
このように感じている方は多いのではないでしょうか。
一寸先が読めず、変化の激しいVUCAの時代において、企業にとって1番大切なことは「外部環境の変化に適応するために、自らも変化し続けること」。
つまり、外部環境の変化をいち早く「感知」し、「判断」し、「行動」に移すことが重要なのですが、
この「感知→判断→行動」のサイクルを早く回せる組織のみが存続することができるのだと森岡さんは主張します。
そんな森岡さんが理想とする組織は、「人体のような組織」。
人間の臓器は、脳や心臓はもとより何一つ無駄なものはなく、それぞれの臓器が自らの役割を果たしつつも有機的に結び付く(共依存関係)ことによって、人体の活動を保っています。



「人体のような組織」はとってもわかりやすい例えでした。でもそんな理想的な組織はどうやって作るんだろう…….
会社を支える4つの機能
そもそも、会社はどのような機能で成立しているのでしょうか。



営業、企画、生産、総務、人事、バックオフィス……
たくさんの部署があるよね
森岡さんは、会社は以下の4つの機能で成り立っていると述べています。
- マーケティングシステム
- ファイナンスシステム
- 生産マネジメントシステム
- 組織マネジメントシステム
ちょっとだけ補足すると、❶マーケティングシステムには、商品開発から営業までが含まれます。
よく、商品開発とマーケティングを別部署にしている会社がありますが、
それでは機能しない、というのが森岡さんの持論。
市場分析に基づく顧客ニーズと離れた商品を開発しても絶対に売れません。
❷ファイナンスシステムは、企業活動に不可欠なお金全般を扱うシステムです。財務とか経理ですね。
❸生産マネジメントシステムは、商品を継続的に生み出し続ける一連の機能のことで、自動車産業をはじめ日本企業の多くが強みを持つ分野です。
そして、本書のメインテーマが❹組織マネジメントシステム。人をより効率的に働かせるための仕組みを最適化するシステムのこと。


それでは、組織マネジメントによって、他の3つの機能を有機的に結びつけるにはどうすれば良いのか。
人間の本質と組織マネジメント
まず、会社と社員が求める方向は明確に異なるのだということを認識する必要があります。
会社が存続していくためには、常に外部環境の変化に順応するために自らも変わっていく必要があります。
一方、社員は変化を嫌います。これは、良し悪しの問題ではなく、人間はリスクを避ける生き物であり、大きな変化を拒む、「自己保存」が本質です。
この、放っておけば自己保存に陥りやすい社員の本質を仕組みの力で逆手にとることが、組織マネジメントの要諦となります。
具体的には、
- 意思決定のメカニズムを明確にする
- 古典的なアメとムチによる評価・報酬システムを構築すること
の2点が重要であると森岡さんは述べています。
誰がいつ、どこで意思決定を行うのかを明確にする必要があるし、新たなことへのチャレンジや現状を打破する社員の試みは最大限評価する仕組みを作るということですね。
人体のような組織になるために
言いたいことが言えない環境というのは組織にとっては死活問題です。
上司に忖度して部下が本当のことを伝えなければ、会社存続にとって必要な「感知→判断→行動」の基本サイクルが回せません。
最悪の場合、幻覚や幻聴をもとに経営層が重大な決断をしてしまうことも……
これでは、変化の激しい現代を生き抜くことはできなくなってしまいます。
人体のように人が共依存関係にある活気ある組織にはなるためには、
年齢差や上司部下、性差による上下関係などはなく、平等であるという認識を持ちつつ、年控序列であったり、成果に対してしっかりと評価、報酬を支払うルールを作る必要があると森岡さんは述べています。



上司の役割は意思決定することであって、部下を従わせることではないのです。そうしないと、言いたいことが言えなくなっちゃう



私の勤め先もですが、日本企業も年控序列から能力主義でシフトしてきていますね〜


社内で提案を通す魔法のスキル
本書の後半は、1社員という立場から、如何にして自分の企画を組織の中でカタチにしていくか、がテーマになっています。



企画を担当された方はわかると思いますが、規模の大きな会社で新しい企画を通すのって本当に骨が折れますよね……
社内マーケティング
社内に自分の企画を通す考え方には、マーケティング手法が応用できるというのが森岡さん流のフレームワークです。
自分が「売りたい」というもの(提案)を如何に社内を顧客に見立てたマーケティングです。
そのステップは以下のとおりです。
会社の目的に沿ったものでないと、企画は通らない。スタート地点はこの当たり前のルールを理解すること
次に、会社が目指している戦略を軸にして自分の企画を考えてみる。勝つ確率が高い戦いを選択することが重要
社内の意思決定者は誰か。社内のパワーバランスを正確に把握する。上司にまず提案することになりますが、上司は上席からのミッションを背負っていることを意識する
上司の便益は何か。その上席者の便益は何か。自分の味方につけるためのストーリーをしっかりと考える
言いたいことを相手が聴きたいように話す
ざっくりとまとめるとこういうことですが、最後のHOWの部分について詳しく解説します。
ヒトには4つの型がある
自らの提案を社内に通すためには、社内政治の荒波を乗り越えることが必要。
相手によって説明の仕方を工夫する必要があることは経験上わかると思いますが、人には大きく4つの型があると森岡さんは述べています。
4つの型とは、❶攻撃型、❷積極型、❸反応型、❹消極型。
攻撃型と積極型はPush型、反応型と消極型はPull型に分類されます。
それぞれの特徴はざっくりと以下のような感じ。
攻撃型


- 人の話を聞かずに自分の意見を押し通す
- ハラスメント気質
積極型


- 相手の主張も受け入れながら、自らの提案を推す
反応型


- 相手の話をまずは聞き入れ、追加の改善提案を行う
消極型


- 自ら提案や発信することはない
- 無関心
まず、自分が4つの型のうちどれに当てはまるかを把握してみましょう。
1つの型のみに偏るということは稀で、森岡さん自身は攻撃型と積極型の両方の性質を持っていると認識されているそうです。



私は攻撃10%、積極30%、反応40%、消極30%くらい
自分の型を把握したら、次は相手のタイプ判定です。
特に、提案する相手が攻撃型や消極型の場合は少し難易度が上がるのでしっかりと作戦を練る必要があります。
まともな議論にならない可能性があるからです。
攻撃型の人には、「相槌を打つ」、「相手の主張を一旦受け入れる」などで、なんとか「積極型」へ誘導してみたり、
消極型の人には、「この件について〇〇さんはどう思いますか?」とオープンクエスッチョンを多用し、反応型に誘導する必要があります。



組織論の本はたくさんあるけど、マーケティングの論理に当てはめてしまうのが森岡流。本のタイトルの意味がわかったぞ
まとめ
いかがだったでしょうか。
本書の内容をまとめると、以下の2点です。
- 変化し続ける組織を作るには、人間の本質である「自己保存」を逆手にとる仕組みづくりが必要
- 社内で自らの企画や意見を通すためには、マーケティングの発想に立って、相手(市場)を知り、相手が求める文脈(ニーズ)に紐付けた方法を選択する必要がある



忘れてはいけないこととして、最後に会社を動かすのは、熱い想いだったりパッションだったりします
本書も、相変わらずの森岡節。心が温まりました。
本なのに、なぜか目の前で森岡さんの講演を聞いているような臨場感があって引き込まれちゃいます。
森岡さんの文章力は、本当見習いたいと心から思いますね。
「マーケティングとは組織革命である」、期待通りの良書でした。
皆さんもぜひ、本書を手に取ってみてください。



最後まで読んでくれて、ありがとうございました〜。
記事を気に入ってくれたら、SNS等で拡散していただけると大変嬉しいです
森岡さんの本はこちらの記事も参考にしてみてください。
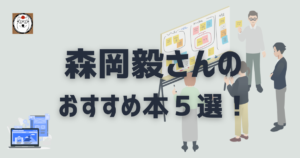
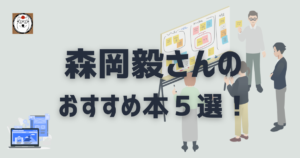
\ にほんブログ村参加中〜クリックしてね/
\1ヶ月の無料体験実施中🎵/
Amazonのオーディオブック Amazon Audibuleはこちらから